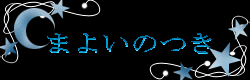

月を見る。月もわたしを見る。何度も、何度も月を見る。
でも、その月はいつも同じ顔をしてはいない
月は日ごとやせ、日ごと太る。日ごとに変わる
月
まるで自らの姿を、ひとつに決めかねているように
月は変わる
わたしは迷う。いったい月の何を信じればよいのかと
そして聞く。わたしは誰?と
「疲れてはいないか?真珠姫」
前方を歩く人影が振り向き、私に聞く。砂のマントが風を受けて翩翻とひるがえり、境目がそのままあたりの空気に溶け込む。わたしは、返事をしなかった。彼の声が届いていない訳ではなかったけれど、何を言っているのか、おそらく認識していなかったからだろう。
わたしは、また、考え事をしはじめていたから。
考えることは、いつも同じこと。いくら考えても答えが出ないということも、いつもと同じ。そして、彼がわたしを心配することも。
「真珠姫?聞いているか?大丈夫か?真珠。」
彼が砂のマントをはためかせ、振り返り数歩遅れてついてきていたわたしのほうに歩み寄る。陽光に「核」が煌いた。青い。青い輝き。どこか冷たくて、冴え冴えとしていて、どこまでもまっすぐに届く青い輝き。
彼はわたしの頬に右手を差し出そうとして、ふと気づき、あわてて反対の手を差し出して、触れた。わたしはその感触にわれを取り戻して、触れられることの無かった彼の右腕に自分の手を触れさせた。固くて、冷たい感触が歩き続けて火照った体に心地がよい。
彼の手も、ほかの「生き物」に比べれば、ずいぶんと冷たいのだけれども。それから、わたしの手も。
「真珠?」
返事の無いわたしに、彼の声はあくまで優しい。「瑠璃君…」と、わたしは彼の名前を呼んだ。
「瑠璃くん。わたしは大丈夫よ?」
頬に触れる左手の仄かな冷たさと、手に触れるこちらのわずかな熱を全て吸い取るような温度の硬く、蒼い右腕がわたしの心を波立たせる。理由のわからない、甘い疼き。名前の知らない感情。すべて、全てこの目の前の彼に帰結する。瑠璃くん。
「無理をするな。」まだ少年らしさの抜け切らない、それでも男性として十分に低い声。
「核が、少し濁っている。もうすぐ町だが、少し休むか?」
わたしは首を小さく振った。そしてわたしはわたしの核を見る。白い、白い輝き。ひそやかな月の光のような、仄かな輝き。曖昧で真実の無い月に似た。
わたしたちは、「珠魅」普遍の強さと、儚い脆さを併せ持つ種族。緩やかに滅びの道を歩み行く種族。
珠魅の発生については、いろいろある。もっとも広く信じられている説は宝石と呼ばれる石達が長い年月をかけて感情と人格を身に着け、その石にもっともふさわしい姿を身にまとうと言うもの。でも、わたしも瑠璃くんも珠魅だけれども、本当のことはよくわからない。でも、いわゆる「つがい」から生まれていないということだけは確か。だから、みんなの言うように「両親」というものは、わたしにとっては無縁の言葉。別段、寂しいと思ったことは無い。それが当然のことだから。
珠魅は信じられている生まれを示すかのように、鎖骨の下のあたり、すなわち心臓に当たる部分に「核」と呼ばれる物質が突出している。「核」はさまざまな宝石の形態を持っている。例えば、瑠璃くんであればその名が示すとおり青く輝く大きなラピスラズリが瑠璃くんの核だ。わたしはやっぱり名前のとおり真珠がそのまま核になっている。おおきな、白い真珠。それがわたしの核。
珠魅は石の化身と言って良い。だから寿命はうんと長い。永久に行き続けるって言う人もいるくらいに。それも変わらぬ姿のまま。生まれてこのファ・ディールの世界に現れたときのまま、変わらずに、ずっと。
けど、そんな珠魅にも弱点はある。それは核だ。核を傷つけられたら、たいていの珠魅は瀕死になる。核が無くなったら、珠魅は死ぬ。死ぬと言うのは、ふさわしくないかもしれない。ただ、身体を失うだけだから。でも、それは生きているとはいえるのか、わたしには、よくわからない。身体は、まるで初めからいたことが幻だったように珠魅の肉体は残らない。塵のように風にまぎれてしまう。
まるで世界に憎まれてるかのように。
核の輝きはそのまま、その珠魅を表わす。健康で何の曇りも無ければ核は冴え冴えと輝き渡るし、体にどこか害をなしていれば、濁り鈍く光る。
そんな不思議な核の存在を多種族が目に付けない訳が無い。事実、大きな宝石でもある核を求めて、多くの珠魅が狩られたらしい。そして、その核をおおっぴらとはいえないまでも売りさばく店もあったほどだと言う。
そんな悲劇的な「珠魅狩り」のせいもあってか、珠魅の総数はさほど多くは無いようだ。どうしてはっきりしたことがいえないのかと言うと、わたしも瑠璃くんも、詳しいことは何も知らないから。今までの旅でとても昔に大きな戦争があったと言うこと、ひんぱんに行われていた「珠魅狩り」の事、滅んでしまったらしい、珠魅だけの都市のこと。それから、最近活躍している宝石泥棒のうわさだけを聞いた。宝石泥棒は珠魅の核を盗んでいるらしい。ただ一人で行っている「珠魅狩り」誰もその理由を知らない。
わたしと瑠璃くんは仲間を求めて旅をしている。まだ、ファ・ディールのどこかには珠魅がいるんじゃないかと思って。仲間を得ることができれば。瑠璃くんは、その先は何も言わないけれど、わたしにはわかる。仲間を、珠魅の仲間を得ることができれば珠魅の都市が滅びた謎も、誰かが教えてくれる。そう考えているんだと思う。瑠璃くんは、とても若い。たぶん、年齢も見かけの年齢とそう変わらないくらい若いのだろう。だから、何も知らない。何も知らないと言う焦りが、いつも瑠璃くんを突き動かしている。
わたし。わたしも何も知らない。どうしてだか、何も知らない。全ての記憶を落としたまま、わたしは砂漠で瑠璃くんに拾われた。それ以来、珠魅の風習に従って、わたしと瑠璃くんはいっしょにいる。戦う力を持つ瑠璃くんはわたしの「騎士」として。闘う力を持たずに、おそらく癒す力を持つだろうわたしは「姫」として。でも、わたしは涙を流せない。
そう。だから、珠魅は滅んでいく種族なのだと、瑠璃くんは苦しげな顔をしてわたしに言った。かつて珠魅は涙を流せた。そしてその涙である「涙石」には全てを癒す力を持っていたらしい。けど、涙石は珠魅の命の欠片。だからこそ全てを癒すことができた。その涙石を、涙を「泣く」と言う感情を、珠魅はなくした。だから、珠魅は癒されること無く、ただ滅んでいくだけ。
そんなことすら、わたしは知らなかった。
「真珠。はぐれるな。」
瑠璃くんの声でわたしはまた、われに帰った。わたしにはとても困った癖がある。考え事をすると、迷子になってしまうのだ。この癖のおかげで、なんど瑠璃くんを困らせたかわからない。それでも、瑠璃くんはいつもわたしを探してくれる。わたしを守るために。それが、わたしの「騎士」としての役目だから。いつもうれしい。うれしいけど…でも、護られるだけじゃ…どうして、どうして嫌なんだろう?
「真珠?また考え事か?」
「ううん。大丈夫。…………ね、手をつないでもいい?」
す、と瑠璃くんを見上げる。わたしより頭ひとつ高い背。綺麗な翠藻色の髪の毛が砂のヴェールマントからはみ出して、切れ長な目の上に軽くかかっている。その、髪の毛越しに見える深くて碧い瑠璃くんの目を見据えてたずねた。
「はぐれるよりは………マシか。」
そういって、瑠璃くんはぶっきらぼうに左手を出す。輝石でできている右手は剣に添えて。ねえ、瑠璃くん。頬が赤いのは、わたしの良いように受け取っても…いいの?
仄かに冷たい手。それがわたしの今の全て。瑠璃くんの手だけが、いまのわたしの。
あたりが、夕暮れに包まれるころわたしたちはようやくドミナの町についた。瑠璃くんは何も言わなかったけれども、おそらく予定よりは遅くなっていたのだろう。いつもわたしは足手まといな気がする。瑠璃くんのお荷物。癒す力の無い姫。わたしは…何のためにいるのか、よくわからないときがある。どうして、瑠璃くんはわたしを護ってくれるのか。何も見返りは無いというのに。癒す力など…涙などとうに失われているというのに。
宿屋の主人の心づくしの夕食をいただき、ひと心地ついた。湯を浴びると一日の疲れがどっと出てきて、いつもだったらすんなりと眠れるのだけれど、今日はなぜだか頭が冴え冴えとしてしまい、色々な事が頭をかすめてゆく。心の中は暗い湖で色々な事が浮き上がってゆくたびに、波打ち、波紋を描く。
わたし……わたしはだあれ?
わたしには記憶が無い。わたしであると言うことの証明は、何一つ無い。ひとが、その人であるという証明が、今までの記憶であるとするのならば、わたしの存在は、まるで嘘のようだと思う。行き場の無い、真昼の月。わたし。瑠璃くんは、わたしのことを真珠と呼ぶ。真珠姫。それがわたしの名前。名前………?
名前と言うものが、この世にわたしという存在をつなぎとめる、絆だとしたら、わたしと言う存在を表わす、ただひとつの本質だとしたら、本当に、わたしは誰なんだろう。本当に「真珠姫」と言う存在は、ここにいるんだろうか。わたしが思っているほど、確かなものなんだろうか?わからない………わからない。なにも。
だって、だって、わかるの。わたしの奥から声がするの。わたしの失った、なくしてしまったはずの記憶の彼方から、わたしを呼ぶ声がする。それは「パール」とわたしを呼んでいる。「真珠」でなく「パール」と。その声は、女性…というよりも少女の声で、その声を聞くとわたしは、少女らしい白くて細い腕と、濃緑色の着物とかそういうものをイメージする。もしかしたら、思い出しているのかもしれない。
濃緑色の着物の隙間から傷ついた弱々しい輝きが見える。誰かの…わたしをパールと呼ぶ彼女の…核だろうか。それとは別に、また緑とも、紫ともつかない輝きのイメージも見える。それから…………黒。誰に属すともわからない、黒い輝き。漆黒の輝き。
その漆黒の輝きは、たやすくわたしの一部分とつながり、暗い湖となってわたしに問いかける。わたしは…誰?と。思い出しなさい、とわたしに告げる。わたし…わからない。こわい。こわいの。何が?思い出すことが?どうして、思い出すことが怖いの?失われそうだから?何が?…………………わたしが?
真珠、と言う宝石は、いろんな色がある。白、黒、黄、桃…………わたしは白。どうして……どうして白いだけなの?どうして………?
「どこへ行く?」
ふっと、凍りつくような声をかけられる。そうして、初めてわたしは寝台から出てふらふらとさまよい出ていることに気付いた。外は煌々とした月夜で、月は窓越しに緩やかな光の腕を差し伸べている。そのうす暗がりの中で、瑠璃くんはわたしの手首を痛いほどにつかみ、わたしをしっかりと見据えていた。
「眠れないのか?また…考え事をしていたな?」
瑠璃くんは、怒っている。きっと怒っている。わたしがまた、迷惑をかけたから。
「ご……ごめんなさい。すこし、考え事をしてたら……眠れなくなったの……だから……」
「何も、考えなくていいと言っただろう?」
びくり、とわたしは思わず身をすくませた。怒られる、と思ったから。でも。
「オマエは、俺に、ただ守られていれば良い……それだけだ。それだけでいいはずなんだ。」
そういって瑠璃くんは、わたしを抱き寄せた。小鳥を扱うよりも、もっとやさしく。花を扱うよりも、もっと甘く。
「る……瑠璃くん………」
わたしは、少し戸惑った。でも。でも。
「……………でも。」と、わたしは瑠璃くんの腕の中で、弱々しく抗議する。
「でも、なんだ?」
「わたし…………わたしは、誰なのか…しりたいの……」
誰でもない、と瑠璃くんは言った。両の腕に力を込めながら。
「オマエは真珠姫だ。俺の姫だ………俺に、守られるべき存在だ。どこにも、いかせない。」
じゃあ、どうして。とわたしは聞きたくなる。どうして、そんなに瑠璃くんは不安そうなんだろう、と。どうして、わたしより、わたしの過去が怖いの?わたしは、わたしの今も、未来も怖い。昔のことが、霧の向こうのようにわからないから。何も見えなくて、それに、触れることすらかなわない。いたずらに風が吹いた時だけ、その姿を垣間見せるいじわるな、昔。
「オマエは……俺に守られていろ。真珠………」
瑠璃くんがわたしの唇に触れた。ほのかに冷たい手。そのまま唇が重なる。唇も冷たい。手のひら程度には。
ああ、珠魅なんだな、と思う。他の生物には無い独特な冷たさ。瑠璃くんの柔らかな左手はわたしの髪を、耳朶をくすぐる。ふと、体の奥がぽっと温かくなる感じがして、わたしは吐息が確実に温まっていることを実感する。
んっ…………。
「オマエは……俺が守る。だから、どこへもいくな………真珠」
どこに?わたしがどこに行くというんだろう。瑠璃くんの手のひらが全てなのに。その、瑠璃くんの手のひらは、そのままわたしの胸のふくらみの上でとまる。戸惑うような逡巡のあと、瑠璃くんはわたしのふくらみを優しくつかんだ。
「あっ………るりくん。」
思わず声を上げる。瑠璃くん。瑠璃くんの手のひら、やっぱり冷たいね?瑠璃くんは優しく、でも、だんだんと大胆にわたしの胸を揉み始めた。
「んん…………んっ」
瑠璃くんの手のひらの動きに合わせて、わたしの乳房はその柔らかさを誇示するようにさまざまな形になる。上を向いたり、下を向いたり。
初めてじゃない。瑠璃くんと、こうすることは初めてじゃないけど。でも、まだ少し照れてしまう。恥ずかしいよ、と瑠璃くんに言う。
「初めてじゃないだろう?」
そうだけど。そうだけど。でも。
瑠璃くん。キスして欲しいよ。ねえ、キスして?
わたしの心がわかるように、瑠璃くんは離れていた唇を重ねてくれた。他の何とも似ていない弾力をわたしは白くなり始めた意識の中で味わう。ああ。瑠璃くんの唇なんだな。って。
そのまま舌を絡めあうと、ぴちゅぴちゅとかすかな水音がした。なんだかとってもどきどきする気がする。どうしてだろう?
瑠璃くんの歯を舌でなぞる。瑠璃くんもわたしの歯を舌でなぞる。ううん。歯だけじゃない。口の中ぜんぶを舌でたどる。なぞる。唾液が交じり合って、わたしはのどを鳴らした。瑠璃くんの…なんだか甘い気がするの。どうして瑠璃くんの口の中は甘いのかな?
するり、と肩から何かが滑り落ちる感覚がする。それはもちろんドレスで、わたしの白いドレスは引き下げられ、両方の乳房があらわになる。ぷくんと何かの果実のようなふくらみ。
うふ。なんだか可愛いね。
自分のおっぱいを見て、そんなことを思う。だって、瑠璃くんにこんなことされてるんだもの。可愛くないはずが無い。うん。すごく…可愛い気がするの。可愛いって、だけじゃなくて。可愛いって、だけじゃないんだけど。でも。
「ふふ………」
言葉が見つからなくて、でもなんだかくすぐったくてわたしは、思わず微笑った。
瑠璃くんは、わからないって顔をして、わたしの目を覗き込む。でも、別にわたしの目の中に答えが書いてあるわけじゃないから、だから瑠璃くんは答えを求めることはやめて、首筋に下を這わせてそのまま胸までたどった。
「んっ。」
乳首が。乳首が刺激されると、どうしてこんなにきゅんってするのかな。神経が、血が、体の一部分に集まる感じ。あっ。ああっ。
瑠璃くんの右手は、左手よりも冷たくて、硬い。だって、石でできているから。でも、その手が、一生懸命優しくしようとしてくれてるの、よくわかるの。わたしのおっぱいをつかむ時、そのごつごつした感じが、とってもどきどきする。
「ふぁ……あぁ………んぅ」
こらえていた声が、思わず出た。くらり、とどこかに飛ばされるような感覚。
瑠璃くんは、まだ執拗にわたしの乳房をいじっている。
「真珠………まだ、少し小さいな。」
うん。いいの。小さくても。だって。
「でも………充分だ。やわらかいし、形も綺麗だからな。」
瑠璃くんは、他の人のを見たことも無いのに言う。でも、いいの。嘘でもいいの。だって、いとおしんでくれてるんでしょう?それが全てで、それ以外のものはいらない。
「こんなに形を変える。………かわいいな?女の乳房は。」
うん。かわいいよ。だって、瑠璃くんにそんな風にしてもらえてるもんね。
「あん。ああっ。うんっ………もっと、もっとして……?ね、もっと………」
こらえきれなくなってわたしはねだった。気持ち良くなりたい、だけじゃなくて。もっと。
「ああ。真珠。しんじゅっ………」
熱に浮かされてるみたい瑠璃くん。それとも、夢見心地って、こういうのを言うのかな?必死にわたしの身体にすがりつく。
かつん。と核と核が触れ合う。ああっ。瑠璃くんの青と、わたしの白。いつもは白い核だけど、今はほのかに桃色がかっている。ピンクパールへとわたしの真珠の核は、少しずつ変貌している。いつもそう。瑠璃くんに抱かれると、わたしの核は桃色に変化する。
どうして、どうして黒じゃないんだろう。…………わたしの黒は、何処?
「感じて……いるな。」
そういって瑠璃くんはわたしのピンク色に変わった核をなめ、唇の弾力で刺激し、甘噛みをする。核への愛撫は体の何処を愛撫されているのとも違う感覚がする。もどかしいような、ひどく敏感なような。どちらともつかないすごく曖昧で、奇妙な感覚。
「あんっ……あんっあんっあんっ…きもち………いいの……いいのっ。瑠璃くんっ!」
もう、おかしくなってしまいそう。わたしの核。瑠璃くんの核。二つとも、仲良く輝いている。心地のよさに。
瑠璃くんっ。
瑠璃くんの肩は、いつの間にかむきだしになっていて、いつもは冷たい身体がほんの少しあったまってるのを感じる。
わたしも、瑠璃くんに気持ちよくなってもらいたいから、だからわたしも青い核に口付けして、舌を懸命に這わせた。
「ああ………真珠…………」
瑠璃くんが、わたしの名前を呼ぶ。この声が、わたしをこの世につなぎとめてるんだ。そう思うとなんだか鼻の奥が、つぅんとして、泣きそうなんだなって思った。
瑠璃くん、瑠璃くん、瑠璃くん、瑠璃くん瑠璃くん瑠璃くん瑠璃くん瑠璃くん瑠璃くん瑠璃くん瑠璃くん瑠璃くん瑠璃くん瑠璃くん瑠璃くん瑠璃くん瑠璃くん瑠璃くん。
……………………………………すき。
好きなの。好きなの。好きなの。護ってもらうだけじゃ、いやなの。こうして欲しいの。もっと、もっと。でも、でもいえないの。好きになって、なんていえない。いとおしんで、なんて言えない。迷惑ばかりかけてるから。でも。でも。
いまだけ。いまだけでいいから。せいいっぱい。わたしを。
「ひぁっ!」
瑠璃くんの柔らかいほうの手が、わたしの一番奥にまで伸ばされる。身体の奥。人はここから生まれてくるけど。でも珠魅は違う。
どうして、こんな器官があるんだろう。何でかな?きっと気持ちよくなるためだけにあるんだね。珠魅って、本当はなんだかとってもいやらしい種族なのかな?だって、子供を生まないのに、こんなことが出来ちゃうんだもん。
でも、もしかしたら、すごく、すごく純粋なのかもしれないね。だって、目的が無いんだもん。ただ、こうするってだけの、それ以外の目的が。
「ううん。あぅ…………」
舌の上にほのかな塩味を感じてわたしは、自分が涙を流してることに気付いた。
「声をひそめろ。真珠。これでは隣の部屋にまで聞こえてしまうだろう?」
いじわるな瑠璃くんの声。でも、だって、こんなんじゃ、声を出さずに入られない。だって、ああっ。あん。あん、あん、あんっ。
白くなる。どんどん白くなる。わたしの頭の中。
くちゅって、瑠璃くんの指の幾本かが、わたしの身体の中に入る。ちょっとした圧迫感。残りの指は一番敏感な突起に添えて、そのままゆっくりとわたしの中からあふれ出る液体を、外にかきだす。わたしのはしたない器官は瑠璃くんの指の動きにあわせていくらでも水を湧かせる。
そこは、もう、すごく熱い。もちろん、珠魅の身体の中にしては、だけど。でも、瑠璃くんの指が、とても冷たく感じるから、熱く、熱くなってるんだろうなって、そんなことはわかる。
「ひぁ、う。んんっ………ねっ……るりくんっ……ちょうだい?」
身体の下で。瑠璃くんの身体の下で、わたしは両腕を広げてねだった。いつも来ている白いドレスは、もうどこかへ行ってしまって、素裸のわたしが、ただベッドの上で瑠璃くんにおねだりをしている。
ね?もう、いいよね?
瑠璃くんは刹那、うっとりと見とれるような陶酔の表情を見せて、わたしの身体を折れんばかりに抱きしめる。ああっ。壊れちゃう。ほんとに壊れちゃうよう…瑠璃くん。
瑠璃くんの屹立がわたしの中に入り始めるのを、ぼんやりとしながら、感じる。
ん。今入り口。ああ、あ。入ってくる…入ってくるよう。うう、う。うんっ!あ……あぁん、ああ、いっぱい、いっぱいね。わたしの中、瑠璃くんでいっぱい…。
頭の中…イメージが浮かぶ。瑠璃くんのにわたしのが、ひだひだって、くちくちって絡み付いてる。そんな…そんなイメージ。
「ああっ…………瑠璃くんっ…………」
瑠璃くんの。瑠璃くんのあそこ。女の子と、わたしとこうするためだけにある、特別な、特別な器官。わたしの膣内も瑠璃くんの石の右手のように硬くなった「そこ」をいっぱい、いっぱい締め付ける。
わたし、いま、身体いっぱい瑠璃くんを感じてる。理屈じゃなくて、そう思った。
動かすぞという厳かな宣誓のあと瑠璃くんは、ゆっくりと抽躁をはじめた。もう、いっぱいいっぱいだと思っていたのに、それでもわたしの身体はもっともっとって、ねだってる。もっと、気持ちよくなりたいって。もっと気持ちよくなれるよって。
「あぁ………いいよぅ。瑠璃くん。もっと……もっと動かしてっ……いいっ…あっ。あんっ!」
もっと激しくして、いいから。ねえ?
瑠璃くんは、わたしの訴えを受けて、激しく腰を動かし始めた。ずぷずぷずぷって、何の音だろうと思っていたら、わたしと瑠璃くんが立てている音だっていまさらながら気付いた。こんなに音が立つくらい、わたしたちしてるんだね。ああっ。あ。あ。あ。あ。ああ。
「真珠………真珠ッ!!」
瑠璃くんの声は、普段の時よりずいぶん上ずってて、わたしの身体に溺れてるんじゃないかって、幸福な錯覚を抱かせる。うぬぼれたい。うぬぼれていたい。今だけでいいから。
「あっ……壊れちゃう………壊れちゃうっ………んっんっんっんっんっ!!!!!」
壊して。壊して。わたしをこのまま壊して。瑠璃くんにだったら、壊されていいの。壊されたいの。瑠璃くんに。そして、そしてそのままわたしの欠片を、宝石箱の中に入れて。そしたら、そしたら、もう、いろんな事考えても、瑠璃くんからはなれずにすむよね?もう、瑠璃くんに迷惑かけなくて、すむよね?ああ。ああっ!ああっ!!
白くなる。白くなるわたしの頭の中。何も、もう、何も考えられないの。
『ほんとうに?』
やめて。声をかけないで。
『本当に………何も考えていないの?』
やめて!おねがい。瑠璃くんとこうしていたいの。どうして、どうして許してくれないの。今だけ。今だけでいいのに。先のことなんて、望んでいないからっ………!
瑠璃くんの、ひときわ激しい律動がわたしの頭の中を吹き飛ばした。最高の快楽。同時に瑠璃くんも、びくんと震えてわたしの中で果てた。
汐のように快感が引いていくのと同時に、わたしの頭の中は、漆黒の輝きに包まれた。
『目覚めなさい。真珠姫。』
誰………?誰なの?
わたしは揺り起こされるような感覚を感じて目を覚ました。そこは、漆黒の世界。暗くて、暗くて、少し怖い。怖いのは、きっと暗いだけじゃないって言うのは、頭のどこか冴えた部分で、良くわかっていた。
ふと、目の前に少女が現れた。白いドレス。白い核。珠魅の少女……わたし。わたしが、わたしの目の前に立っている。顔は伏せられていて、見えない。でも受ける印象は、なんだかひどく不穏で、ひどく剣呑だ。こわい。目の前の少女が怖い。わたしであってわたしで無い少女。もう一人の、わたし。あなたは誰?
少女は顔を上げてわたしを見た。やっぱりわたしと同じ顔をしていて、それはひどくわたしを不安にさせる。こわい。これからおこることを見るのが怖い。でも、目を閉じることは出来なくて、目をそらすことも出来なくて。見るしかなかった。核が、核の色が、漆黒に染まってゆくその瞬間を。
白いドレスが、黒いドレスに変わる。目の前の少女はもはや少女ではない。黒い装束は、ドレスだけれども、もっと動きやすい……戦いのための服を身にまとった妙齢の女性。違うのに。何もかも違うのに、顔は似てる。わたしにひどく似てる。わたしが、もっと成長したら……人のように年月を積み重ねたら、こんな風になるだろうって、そんな顔。
『目覚めなさい。真珠姫。わたしはいつもお前の中にいる。そして、わたしの中にお前がいるのだ。』
誰よ!!あなた誰なの!!
『わたしは、パール。レディパール。フローライトの珠魅、玉石姫・蛍の騎士であり、黒真珠を核とするもの。玉石の座の、珠魅。』
黒い女性は、黒いわたしは厳かな声で、そう、言った。
目が覚めた。今度は完全に目が覚めた。「本当の目覚め」に安堵して、手を伸ばした。隣には青い輝きの核がある。瑠璃くんの核。瑠璃くんの、穏やかで規則正しい寝息。
つきは、もうずいぶん西の空に傾いていて、それでも名残惜しげに部屋の中に光を投げかけている。だから、夜目の聞かないわたしでも瑠璃くんの横顔を、つぶさに見ることが出来た。瑠璃くんの横顔。名前と同じ、瑠璃色の核。瑠璃色の髪。今は見えない、瑠璃色の眼。わたしを守る右腕はベッドの上に軽く投げ出されていて、ひどく無造作だけれども、この上なく優しいものに見えた。
わたしは、瑠璃くんに、守られていればいいんだよね?何も考えなくていいんだよね?わたしは、誰かの騎士なんかじゃないよね?わたしは、瑠璃くんの姫でいいんだよね?
『仲間を探す。』
ふと、瑠璃くんの声がよみがえる。瑠璃くんは、仲間を求めてる。そのためにずっと旅をしている。それが瑠璃くんの目的。………でも。でも、もし見つかった仲間が、姫だったら。どうしよう。わたしは……その時わたしはどうするんだろう。瑠璃くんは、どうするんだろう。
『わたしは、いつもお前の中にいる。』
いや!いや!いや!いや!いや!
仲間なんか、見つからなければいい。そしたら、ずっと二人でいられるよね?
「瑠璃くん…………」
わたしは、わたしの騎士の身体をしっかりと抱きしめ、夜明けまでの短いひと時を眠りにあてることにした。それは無理かもしれないと、心のどこかでわかっていながら
外は、いまだに月夜。彷徨いの月夜だった。

end
――あとがきめいたいいわけ――
ネタバレ小説な。だから、あとがきもネタバレ。
聖剣伝説レジェンド・オブ・マナ(以下LOM)です。久々にヒットなゲームでした。
絵本めいた水彩画っぽいグラフィック。易しいけど哲学的な内容。
「世界はイメージだよ」って言う言葉に、高校時代の選択授業だった「詩と哲学」を思い出したりしたもんです。
さて、本編主人公の真珠姫は、
LOMの3大ストーリーである「宝石泥棒編」の主人公でもあります。
前半は結構ボケをかましてくれるのですが、後半はひたすら痛ましいのでした。
レディパールも含めて。瑠璃もね。すげー痛ましかったです。
で、赤面症で、おとなしくて、主人公をおにいさま(おねえさま)」と呼び、
瑠璃を「瑠璃くん」と、君付けで呼ぶのには、相当萌えました。萌え萌え。
で、また話が長くなるのですが、書いてて気付いたこと。
わたしはなんだかセックス描写は切ない方がいいらしいです。
「こんなに身体は近いのに、心はけしてひとつじゃないね。」
って言うのが、わたしのセックス描写のひとつのテーマらしいです。
真珠ちゃんの心理描写しながら、「瑠璃くんはもっと君の事好きさ!!」
とか思いながら書いとりました。
だって瑠璃くん、「オマエを宝石箱の中に閉じ込めてしまいたい」
とかゆーし(うろ覚えですが)。
ゲーム本編後半で。
彼女が、レディパールであり、最強の騎士(確実に自分より強い)であるとわかっても。
このころの瑠璃くんは「真珠姫を守ること=自分のアイデンティティー」なんで、
どーにもこーにも仕方ないですが、そんなことしなくても良いんだってわかってからは、
よかったなあ、とか思いました。
もうホント最後の最後でレディパールが「わたしの騎士」
って瑠璃くんを言っていたのにはうれしかったです。
「守る」「守られる」って言うことに強さは関係ないんだなあって。
レディパールの凛とした強さも好きですが、
真珠姫のなよやかさも、弱々しさもすごく好きです。
LOMは名作ゲームだぜ!!
すくえあ臭がぜんぜんしないなあ、とか思っていたら製作スタッフ達がニンテンドーに引き抜かれたのには大笑いすくえあ大ぴんち。
ニンテンドーから新しい聖剣ブランドが出るのかと思うと、もうどっきどきですね。
(多分でないけど)
まあ、あとがきも長くなってしまいました。エロ描写はあいかわらず薄いんで、
なんだろ「エロのある少女小説」とかそーゆー感じでひとつ。(ひとつじゃねえ)
しかし、真珠姫「無知と無垢の、両方が当てはまる」ってはずだが、両方あてはまんねえなあ。
あらら。
あ、もちろん真珠の核が気持ちヨクなるとピンク色に変わるのは、オリジナルです。ごめんね。
